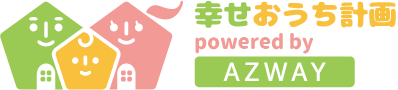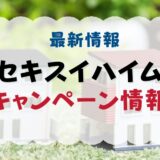promotion
<記事の情報は、2023年7月26日時点のものです>
「一戸建てのマイホーム」は、多くの人が思い描く憧れ。
中でも自分たちの好みや暮らし方に合わせてつくる注文住宅は、夢が詰まった理想の住まいです。
家づくりを考える時、最も気になるのはやはり費用のこと。
特に初めての家づくりの場合、不安も多いのではないでしょうか。
家づくりにかかる費用は、土地の有無・建てる地域・家の広さなどによって大きく変わります。
また、ローンで借り入れできる金額は、自己資金の額や年収によって変動します。
「全部でいくらかかるの?」「自分たちの収入で払っていける?」「今の予算だとどんな家が建てられる?」といった疑問に答えるべく、費用の内訳や予算の考え方など基本的な情報をまとめました。
家づくりの第一歩は情報収集から。
正しい知識を身につけて、理想の住まいを手に入れてください。
また、解説に入る前に家づくりを失敗させないために1番重要なことをお伝えします。
それは、1番最初にマイホーム建設予定に対応している住宅メーカーからカタログを取り寄せてしまうこと。
これから30年、40年と生活をするマイホーム。絶対に失敗するわけにはいきません。
家を建てようとする人がよくやってしまう大きな失敗が、情報集めよりも先に住宅展示場やイベントに足を運んでしまうこと。
「とりあえず行ってみよう!」と気軽に参加した住宅展示場で、自分の理想に近い(と思い込んでしまった)家を見つけ、営業マンの勢いに流され契約まで進んでしまう人がかなり多いのです。 
はっきり言って、こうなってしまうと高確率で理想の家は建てられません。
もっと安くてもっと条件にあった住宅メーカーがあったかもしれないのに、モデルハウスを見ただけで気持ちが高まり契約すると、何百万円、場合によっては1,000万円以上の大きな損をしてしまうことになるのです。
マイホームは人生の中でもっとも高い買い物。 一生の付き合いになるわけですから、しっかりと情報収集せずに住宅メーカーを決めるのは絶対にやめて下さい。
「情報収集しすぎ」と家族や友人に言われるくらいで丁度良いのです。
とはいえ、自力で0から住宅メーカーの情報や資料を集めるのは面倒ですし、そもそもどうやって情報収集すればいいのか分からない人も多いでしょう。
そこでおすすめしたいのがリクルートが運営する、「SUUMOの無料カタログ一括取り寄せ」(工務店中心) そしてNTTデータグループが運営している、「家づくりのとびら」(ハウスメーカー中心)
家を建てる予定のエリアや希望条件を入力するだけで、条件にあったハウスメーカーや工務店がピックアップされ、まとめて簡単に無料でカタログを取り寄せられます。
SUUMOはポータルサイトのネットワークを活かし、全国の工務店をカバー。 NTTデータグループは、老舗大手の信用を活かし、ハウスメーカー中心。
メーカーごとの強みや特徴が分かりますし、複数社で価格を競わせることで全く同じ品質の家でも400万.500万円と違いが出ることさえあります。  また、どちらの会社も共に日本を代表するプライム上場企業グループが厳しい審査をしているのも大きなメリット。
また、どちらの会社も共に日本を代表するプライム上場企業グループが厳しい審査をしているのも大きなメリット。
厳しい審査に通った優良住宅メーカーのみ掲載が許されているので、悪質な会社に騙されたりしつこい悪質営業をされることもありません。
後から取り返しのつかない後悔をしないよう、家を建てるときには面倒くさがらず1社でも多くのカタログを取り寄せてしまうことをおすすめします。
それでは、本文の解説をしていきます。

【本記事の監修者】 宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー 大学卒業後、東証一部上場大手保険代理店へ入社。その後、大手不動産ポータルサイト運営会社へ転職。ITベンチャー企業での経験を経て株式会社Azwayを創業。 「住まい」と「ライフスタイル」に特化したWEBサービスを手掛けている。
もくじ
注文住宅にかかる費用相場を地域別に紹介

一言で注文住宅と言っても、建築にかかる費用は地域によって大きく異なります。
その理由は大きく分けて
1.土地の価格が違うため
2.家の広さが違うため
の2点です。
もともと土地を持っている場合をのぞき、住宅建築のためには土地の取得が不可欠です。
言うまでもなく、土地の価格は首都圏をはじめとする大都市圏ほど高く、地方に行くほど安くなります。
そのため、都市圏では比較的コンパクトな住宅が密集する傾向にありますが、地方では広い敷地に庭付きの大きな家が点在するという大きな違いがあります。
それでは、注文住宅にかかる地域別の費用相場はどの程度でしょうか。
住宅金融支援機構による「2018年度 フラット35利用者調査」(長期固定金利の住宅ローン「フラット35」の申込77,680件のデータから集計)によると、地域別の土地取得費+建築費の平均は下記の通りです。
全国平均 土地 1335.1万円 + 建築費 2777.5万円 = 合計 4112.6万円
首都圏 土地 2145.8万円 + 建築費 2628.9万円 = 合計 4774.7万円
近畿圏 土地 1574.9万円 + 建築費 2652.4万円 = 合計 4227.3万円
東海圏 土地 1208.2万円 + 建築費 2898.3万円 = 合計 4106.5万円
その他地域 土地 897.0万円 + 建築費 2865.1万円 = 合計 3762.1万円
となり、首都圏とその他地域では約1.3倍もの差があることがわかります。
| 地域 | 土地 | 建築費 | 合計 |
| 全国平均 | 1335.1万円 | 2777.5万円 | 4112.6万円 |
| 首都圏 | 2145.8万円 | 2628.9万円 | 4774.7万円 |
| 近畿圏 | 1574.9万円 | 2652.4万円 | 4227.3万円 |
| 東海圏 | 1208.2万円 | 2898.3万円 | 4106.5万円 |
| その他地域 | 897.0万円 | 2865.1万円 | 3762.1万円 |
参考記事⇒ 2018年度 フラット35利用者調査
注文住宅の費用の内訳を一覧で紹介!

地域別の相場がわかったところで、費用の内訳を細かく見ていきます。
注文住宅を建築する際に必要な費用は、大きく「土地」と「建物」に分かれます。
土地購入にかかる費用一覧
土地を購入するためには、土地代のほかに様々な費用が必要です。
仲介手数料
多くの場合、土地の売買は不動産会社を通して行います。
不動産会社は、土地の所有者と購入者を結び付け、契約を成立させることで利益を得ます。
土地所有者を紹介してもらう対価として支払うのが仲介手数料です。
仲介手数料の金額は、売買価格帯ごとに宅地建物取引業法で上限が定められています。
住宅建築用の土地売買で一般的な400万円以上の場合、
(売買価格×3%)+6万円+消費税
という算出式で求められます。
例えば2000万円の土地を購入する場合、仲介手数料は
(2000万×3%+6万円)×1.1=726,000円 となります。
参考記事⇒ 公益社団法人 全日本不動産協会ホームページ
登記費用
土地を購入するということは、料金を支払ってその土地の所有権を譲り受けるということです。
土地を取得した際には、所有権を正しく登録し守っていくために、不動産登記(所有権の移転登記)を行う義務があります。
不動産登記の際には「登録免許税」が課されます。
税率は土地取得の方法により定められていて、売買により取得した土地の所有権の移転登記を行う場合、税率は2.0%です。
この時、課税額算出の基準となるのは土地の売買価格ではなく、「固定資産税評価額」となるので注意しましょう。
固定資産税評価額は市町村役場で管理されている「固定資産課税台帳」に記載されているほか、固定資産税の納税者および委任を受けた人なら閲覧が可能です。
登録免許税算出の際は1,000円未満切り捨てとなります。
例えば固定資産税評価額が7,654,321円だった場合の登録免許税額は
7,654,000円×2.0%=153,080円 となります。
参考記事⇒ 国税庁ホームページ
登記に必要な書類は自分で作成することも可能ですが、複雑で専門的な知識が求められるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
報酬は司法書士事務所によってさまざまですが、平均して30,000円~50,000円となっています。
参考記事⇒ 日本司法書士会連合会ホームページ
印紙代
売買契約の際、契約書面に貼付する印紙代は契約金額によって決まっていて、土地売買のボリュームゾーンである1,000万円~5,000万円の場合では10,000円です。
固定資産税
土地の所有権が移転した日から、固定資産税が発生します。
固定資産税の請求は売主へ送られるため、移転日から年末までの日割分の金額を売主に支払う必要があります。
固定資産税の算出方法は課税標準×1.4%ですが、条件を満たした住宅用地や新築建物は軽減特例が適用されます。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)については課税標準 × 1/6に税率をかけて算出します。
都市計画税
都市計画税は、対象となる区域内の土地の所有者に対して市区町村が課税します。
最高限度0.3%以内の税率で課税されますが、固定資産税と同様に住宅用地には軽減特例があり、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)については課税標準×1/3に税率をかけて算出します。
転用費用
主に地方や郊外で見られるケースですが、購入した土地がもともと農業用地として登記されていた場合、各自治体の農業委員会へ宅地として利用するための申請を行い、許可を受ける必要があります。
農地転用の手続きにかかる費用は10~20万円程度とされています。
土地の位置や登記情報を示す各種書類の取り寄せに1,000円程度、道路や用排水施設の位置を示す図面の作成に数千円、資金力や融資額を証明する書類の取り寄せに数千円程度かかります。
手続きは複雑なため、建築会社や行政書士に依頼するのが一般的です。
その場合は必要経費のほか数千円~数万円の報酬を支払うことになります
また、農業用地は土地改良区と呼ばれる農業組合の管轄下にあることがあります。
土地改良区域内の土地を宅地に変更する場合は、農業用排水施設の新設・管理や水路の整備といった設備の維持管理費を公平に負担するための「農地転用決済金」が発生します。
金額は自治体によって定められていて、1㎡あたり数百円です。
参考記事⇒ 国税庁ホームページ
建物を建てる際にかかる費用
土地の購入、登記と並行して住宅建築の準備を進めます。
建築にかかる費用は工事請負契約の締結時、着工時、上棟時、ローン契約時、引き渡し時などいくつかのタイミングに分けて支払います。
本体工事費用
家づくりの費用で最も大きな割合を占めるのが、本体工事費用です。
文字通り建物本体を建築するための費用ですが、その内訳も細かく分かれています。
仮設工事費用:足場の設営、作業用の電気配線、スタッフのトイレなど工事の準備
基礎工事費用:地面と建物の境目の土台部分
木工事費用:柱や梁といった建物の骨組みの、材料加工と現場工事
防腐・防蟻工事費用:構造部分に防腐材・防蟻材を施工
気密・断熱工事費用:壁や床にウレタン吹付やボード、セルロースなどの断熱材を施工
屋根・板金工事費用:瓦や板金、ガルバリウム鋼板などで屋根を葺き、庇や雨どいを設置
ユニット設備工事費用:システムキッチンやユニットバス、洗面化粧台などを搬入、施工
外装工事費用:サイディングや塗壁で外装を仕上げる
防水工事費用:屋上やベランダから水漏れしないように防水シート、シールを施工
電気・水道・ガス工事費用:電気の配線、給排水、ガスなどの設備
空調工事費用:エアコンや24時間換気システムの導入
内装仕上げ工事費用:クロスや塗壁で内壁や天井を仕上げる
建具工事費用:窓のサッシや室内のドア、障子などの取り付け工事
ガラス工事費用:フィックス窓やガラスブロックなどの取り付け工事
金物工事費用:金属製のドアノブ、手すりなどの取り付け工事
左官工事費用:浴室や洗面のタイルなど、左官による装飾工事
付帯工事費用
建物自体の工事の他、ガスや水道の敷設工事、駐車場や外構の工事、カーテン、照明、冷暖房器具の設置工事などが別途必要です。
これらは本体価格として見積書に記載されていることもあります。
解体工事費用:建築地にもともと建っていた古い家屋を解体、撤去
地盤調査費用:地盤の強弱や状態を確認するための調査
地盤改良工事費用:杭などを打ち込んで地盤を強化し、建物を建てられるように改良
引き込み工事費用:道路から敷地まで、水道管、ガス管、電気配線を引き込む
敷設工事費用:敷地内に引き込んだ水道管、ガス管、電気配線を建物の内部に引き入れる
外構工事費用:駐車場、玄関、アプローチ、塀、門扉など敷地内の屋外工事
造園工事費用:花壇、石垣、植栽、池など庭を造る
特殊設備工事費用:太陽光発電パネルや蓄電池などの追加取り付け工事
屋外空調設備工事費用:エアコンの室外機や換気扇など、設備の外部工事
照明器具工事費用:照明器具の取り付け工事
カーテン工事費用:カーテンやブラインドの取り付け工事
設計費用:設計・デザインのプラン提案
印紙税
土地購入の契約とは別に、工事請負契約の締結時にも契約書を取り交わします。
1,000万円~5,000万円の契約の場合、貼付する印紙の印紙税は10,000円です。
建築確認申請費
建築プランが決まったら、法令や条例に即したプランであるということを確認して許可を受けるため、自治体へ建築申請を行います。
申請自体は建築会社が代行してくれますが、申請費用として10万円~20万円がかかります。
地鎮祭費用
着工前には、地域を守る神様へ土地を使用する許しを願い、工事の安全を祈って「地鎮祭」を行います。
実施は必須ではありませんが、行う場合は神式が多く、地元の神社から神主さんを招いて行い、施主と工事関係者が出席します。
神主さんへの謝礼は「玉串料」もしくは「初穂料」と言い、20,000円~30,000円が相場とされています。
このほか、儀式に必要なお酒、お水、塩、米、野菜、魚などの調達費用で10,000円程度、近隣の方へ配る粗品が1点1,000円~2,000円程度、終了後に宴会を行う場合は飲食費などで数万円がかかります。
上棟式費用
基礎工事が終わり、柱や梁など躯体の骨組みができあがったら、「上棟式」を行います。
屋根の骨組みの最頂部に破魔矢や札を立て、ここまで無事に工事が進んだことを祝うと同時に神様に感謝する儀式です。
支払う金額の相場は10万円前後とされていますが、こちらも必須ではありませんが、工事関係者との絆を深める機会なので、予算が許せば実施しておくとよいでしょう。
上棟式を行う場合、儀式に必要なお供え品の費用のほか、関係者へのご祝儀を用意します。
儀式の内容と祝儀の相場は地域によって差があるので、予め営業担当者などに確認して失礼のないように準備しましょう。
登記費用
無事に竣工したら、建物の不動産登記を行います。
登記には、新築建物の表示登記、所有権保存登記、住宅ローンの抵当権設定登記があります。
表示登記にはかかりませんが、所有権保存登記と抵当権設定登記には登録免許税がかかります。
税率は以下の通りです。
ただし、床面積が50㎡以上で自宅として住む住宅で、2020年3月31日までに取得、居住する場合は軽減税率の対象となり、カッコ内の税率が適用されます。
・所有権保存登記:0.4%(軽減後 0.15%)
・抵当権設定登記:0.4%(軽減後 0.1%)
ローン契約に伴う諸費用
住宅ローンを組んで土地を購入する場合、契約に伴う諸費用が必要です。
諸費用として支払う金額は、およそ土地と建物の価格の3%~7%とされています。
まず、融資を受ける銀行または関連する保証会社へ手数料を支払います。
手数料は数万円に設定されていることが多いですが、中には融資額の2.16%としている会社もあります。
次に、何らかの事情でローンの返済が滞ってしまった場合に保証会社に建て替えてもらうための費用として、ローン保証料というものがあります。
融資額と返済期間によって異なりますが、数十万円という金額が一般的です。
また、ローン契約の用件として火災保険や地震保険への加入が義務付けられています。
保険金額1,000万円あたり10,000円~30,000円が相場です。
不動産取得税
建物の引き渡し後、半年から一年半後に、都道府県から「不動産取得税」の納税通知書が送られてきます。
土地と建物を合わせた固定資産税評価額に基づいて算出され、税率は下記の通りです。
・不動産取得税:固定資産税評価額×4%
ただし、条件を満たした宅地と建物は軽減特例があります。
宅地の課税標準の特例
2021年3月31日までは、宅地の課税標準額は固定資産税評価額の1/2となります。
建物の不動産取得税軽減の特例
床面積が50㎡~240㎡の住宅は、固定資産税評価額から1,200万円を引いた額が課税標準額になります。
土地の不動産取得税軽減の特例
取得から3年以内に建物を新築すると、不動産取得税から下記のいずれか高い方が控除されます。
・45,000円
・(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積× 2(200㎡まで))×3%
複雑な制度ではありますが、正しく申告して軽減措置を受けることで、不動産取得税は大幅に節約できます。
通知書が届いたらすぐに内容を確認し、都道府県の税事務所に問い合わせすることをおすすめします。
注文住宅を購入する際に知っておきたい「坪単価」とは?

住宅の購入や建築時には、費用を表現する際に「坪単価」という表示がしばしば使われます。
坪単価とは、土地価格や施工金額を一坪あたりの金額に割ったものです。
いずれも価格÷面積(坪)で求められます。
ただし、坪単価の算出方法には明確なルールがないため、建築会社によって基準となる面積が異なる場合があります。
施工金額の坪単価の場合、一般的には「延床面積」を基準に算出しますが、法律上延床面積に含まれないバルコニーやポーチ、外構部分も「施工床面積」として算入することがあります。
坪単価で建築会社を比較する際には、どの面積で算出しているのかよく確認しましょう。
注文住宅の費用を実際にシミュレーションした計算例

では、実際に注文住宅を建てた場合の費用を計算してみましょう。
同じ場所、同じ広さの土地をもともと所有している場合と、新規で取得した場合のシミュレーションです
シミュレーション1 Aさんの場合
<条件>
土地:あり
建築地:埼玉県
延床面積:120㎡
敷地面積:160㎡
土地の固定資産税評価額:1,560万円
住宅の固定資産税評価額:2,000万円
入居予定:2020年1月
※土地の所有に関わる費用負担はないものとします。
住宅本体工事 20,000,000円
住宅付帯工事 5,000,000円
不動産取得税 240,000円
固定資産税 140,000円
都市計画税 60,000円
印紙代 10,000円
建築確認申請費 150,000円
地鎮祭費用 45,000円
上棟式費用 100,000円
所有権保存登記 30,000円
抵当権設定登記 20,000円
ローン諸費用 1,500,000円
合計 27,295,000円
シミュレーション2 Bさんの場合
<条件>
土地:なし
建築地:埼玉県
延床面積:120㎡
敷地面積:160㎡
土地の固定資産税評価額:1,560万円
住宅の固定資産税評価額:2,000万円
土地の取得:2019年10月
入居予定:2020年1月
≪土地≫
土地購入費 20,000,000円
仲介手数料 666,006円
登録免許税 312,000円
司法書士報酬 40,000円
印紙代 10,000円
固定資産税 1,170,000円
不動産取得税 0円(軽減特例により)
都市計画税 15,600円
≪住宅≫
住宅本体工事 20,000,000円
住宅付帯工事 5,000,000円
不動産取得税 240,000円
固定資産税 140,000円
都市計画税 60,000円
印紙代 10,000円
建築確認申請費 150,000円
地鎮祭費用 45,000円
上棟式費用 100,000円
所有権保存登記 30,000円
抵当権設定登記 20,000円
ローン諸費用 1,500,000円
合計 49,508,606円
この他、引っ越しにかかる費用や新居での家具購入費などがかかります。
注文住宅を購入する際の予算の決め方・考え方

それでは実際に注文住宅を購入する場合、予算はどのように考えればよいのでしょうか。
住宅ローンの借入額や自己資金比率について説明します。
年収ごとに借り入れできる金額の目安
住宅購入の際には住宅ローンを組むのが一般的ですが、借り入れできる額の限度は年収によって異なります。
多くの金融機関では、年収に占める年間返済額の割合である「返済負担率」を基準にローンの可否を審査します。
年収400未満の場合は返済負担率30%まで、年収400万円以上で35%以上が限度となっています。
これをもとに年収別に借入可能額の目安を表にすると、下記のようになります。
ここでは、年収400万円までは返済負担率25%/30%、それ以上は30%/35%の場合の金額を算出しています。
年収300万円:2,210万円(返済負担率25%)/2,650万円(返済負担率30%)
年収400万円:2,950万円(返済負担率25%)/3,540万円(返済負担率30%)
年収500万円:4,420万円(返済負担率30%)/5,160万円(返済負担率35%)
年収600万円:5,310万円(返済負担率30%)/6,200万円(返済負担率35%)
年収700万円:6,200万円(返済負担率30%)/7,230万円(返済負担率35%)
年収800万円:7,080万円(返済負担率30%)/8,260万円(返済負担率35%)
年収900万円:7,970万円(返済負担率30%)/9,300万円(返済負担率35%)
年収1,000万円:9,510万円(返済負担率30%)/1億330万円(返済負担率35%)
※設定条件:金利1.0%、35年元利均等・ボーナス返済なし
限度額ギリギリまで借り入れをすると、返済中にリスクが発生します。
例えば、主な支払いを担っていた人が病気やケガで働けなくなってしまったり、リストラで収入が減ってしまったり、子どもの進学でお金がかかったりすることがあります。
こうした時に返済できるギリギリの金額を設定してしまっていると、一気に家計が厳しくなってしまいます。
また、金利変動型ローンの場合は、金利上昇によって借入時の想定よりも多く返済しなければならなくなります。
自己資金比率って何?

住宅購入資金のうち、ローンの借り入れとは別に自身で準備する資金の割合が自己資金比率です。
国土交通省の「住宅市場動向調査」によると、自己資金比率は全国平均で28.8%です。
自己資金比率が高いほど金利が安くなり、返済額が少なくなります。
返済のことを考えると、購入資金総額の30%を自己資金で用意し、そのうちの20%をローンの頭金に、10%を諸費用にあてるのが理想的です。
注文住宅を購入する際に費用を削る方法・コツまとめ

注文住宅の購入には多くの費用がかかりますが、工夫次第ではコストを抑えることができます。
土地を相続する
注文住宅購入の費用を考えるとき、土地の有無は大きな差です。
実家の敷地内に建てられるスペースがある、両親から相続できる土地があるといった場合は、活用することでコストを抑えることができます。
転用不要の土地を購入する
農地として登記されている土地の場合、宅地転用に数万~数十万円の費用が必要となってしまいます。
土地を所有しておらず、購入する場合は、宅地として売られている場所を選びましょう。
税金の軽減特例を利用する
不動産の取得には、多くの税金が課税されます。
先に紹介したシミュレーション2でも、200万円近くの税金がかかっています。
しかし、それらの中には、条件を満たすことで軽減する特例が設けられているものがあります。
建築や入居の時期、住宅の性能などによって税額が変わってくるので、建築会社や税理士に相談するのがよいでしょう。
一例として、長期優良住宅や低炭素住宅の基準に適合すると、税制上の優遇を受けることができます。
また、省エネ性や耐震性、バリアフリー性能などを備えた住宅の建築には、防災や健康、子育てに関連する商品と交換できるポイントが付与される「次世代住宅ポイント制度」もあります。
参考⇒政府広報オンライン
シンプルな間取りにする
一般的に住宅の建築では、複雑な間取りほどコストがかかります。
間仕切りの壁や建具などの材料がかかるほか、建蔽率・容積率・斜線規制といった建築法規に合わせて設計する必要があるため設計費がかさむことがあります。
そのため、設計時にできるだけシンプルな間取りにすることで、建築費用を抑えることができます。
素材・設備を使い分ける
内装に使用する素材の選び方でもコストは変わります。
例えば、木のぬくもりを感じられる無垢材の床は人気ですが、フローリングに比べるとコストは高くなります。
家族が最も長い時間を過ごし、来客を迎えるLDKのみ無垢材とし、子ども部屋や寝室はフローリングにすると、材料費を抑えることができます。
同じように、1階の洗面は高級感のあるものを選び、家族のみが使用する2階の洗面は標準的なものを選ぶなど、要所要所でコストをかける部分と抑える部分を決めていくと、建築費用を抑えられるでしょう。
できる部分はDIYする
自分たちの手でできる部分は、専門業者に依頼せずDIYするのも一つの方法です。
土いじりが好きな人であれば、ホームセンターやインターネットで材料を調達し、花壇やアプローチなどの外構を自分でデザインして作り上げることができます。
手洗いボウルや照明などを施主支給で持ち込むこともできます。
1000・2000・3000・4000万円でどんな家を建てられる?一例を紹介

設計や仕様によって住宅建築のコストには幅があります。
予算別に、どのような家が建てられるか、一例をご紹介します。
1000万円
注文住宅において、1000万円台というと最安価格帯です。
中には、本体価格900万円台とうたっている工務店もあります。
この価格帯で建てられる住宅は、いわゆるローコスト住宅やデザイン、仕様がある程度固まった企画住宅が多いです。
延床面積80㎡~120㎡、LDKと子ども部屋2室、水回りなどがコンパクトにまとまった家のイメージです。
地震や断熱は最低限、素材や設備もリーズナブルなものを使い、徹底的にコストを削っています。
必ずしも低価格=低性能というわけではありません。
住宅建築には安全に暮らすための基準がいくつもあり、それらをクリアしたものが販売されているので、予算がないけれどどうしても住宅を建てたいという人にとっては、手の届く価格で建てられる注文住宅といえるでしょう。
ただし、ローコストを売りにしている工務店の中には、本体価格を安く設定しておき、オプションで利益を得ている会社もあります。
どこまでが本体価格に含まれるのか、契約前にチェックしましょう。
2000万円
2000万円台もどちらかというとローコストに分類されます。
設計や仕様は標準的で、部分的にこだわりを取り入れることのできる価格帯です。
ただ、仕入れ価格や施工の工夫でコストを抑える良心的な工務店もあるので、リーズナブルな価格は企業努力の結果ともいえます。
15~20帖のLDKに主寝室と子ども部屋2室、場合によっては趣味室や納戸、ルーフバルコニーも可能です。
ビルトインガレージの場合は3階建てで2階がリビングと水回り、3階にプライベートルームをまとめるケースも多いです。
部分的にこだわりの素材を使ったり、デザインに凝ったりすることも可能でしょう。
3000万円
3000万円の予算があれば、注文住宅らしいこだわりのある家が作れます。
間取りやデザイン、素材も細かくオーダーができます。
どこに予算をかけ、どんな家にするか、選択肢が広がります。
例えば、素材にコストをかけ、無垢材の床や珪藻土の塗り壁など、自然志向の住まいも可能です。
また、キッチンやバスルームなどの設備にこだわりがある人は、グレードアップする余裕も出てきます。
4000万円
4000万円クラスのハイグレードな住まいなら、アプローチに大理石を使ったり、無垢材の中でも高級なウォルナッツを使用したりと、一つ一つの部分に十分な予算をかけられます。
敷地の広さによりますが、LDK、主寝室、子ども部屋など家族の暮らしに必要なスペースのほか、ゲスト用の寝室やオーディオルーム、ガレージなど、プラスアルファの空間を作ることができます。
デザインにこだわりたければ、一級建築士事務所に設計を依頼し、施工のみ建築会社で行うことも可能です。
経験者から学ぶ~注文住宅の資金計画で失敗した人のケース

一生の買い物である住宅購入では、資金計画が非常に重要です。
失敗すると、その後の暮らしに大きく影響することも。
経験者の声を見てみましょう。
貯金を使い果たしてしまった
年収500万円、2,900万円の住宅を購入したところ、ローンの頭金と諸費用で貯金を使い果たしてしまい、手元には20万円しか残らなかった。
借入金額を減らすために頭金を多く支払ったが、その後の引越しや家具購入のことを考えるべきだった。
借り入れ後、予期せぬ出費と収入減
将来のことを考えてローンを組んだつもりだったが、子どもが高校に進学してから、交通費に携帯代、昼食代のほか、部活の遠征やユニフォームにかかる費用が思いのほかかかるように。
さらに夫の転職で収入が減ってしまい家計が火の車になってしまった。
35年ローンの繰り上げ返済ができず、定年後も支払うことに
35歳の時、35年ローンで注文住宅を購入。
途中、余裕ができたら繰り上げ返済するつもりだったが、生活費や教育費がかかり結局繰り上げができず、60歳で定年退職してからも10年間ローンを払い続けることに。
年金以外に収入がない状態で、退職金を切り崩すことになってしまった。
まとめ
注文住宅の購入には、売買価格以外にもさまざまなお金がかかります。
建てる場所、土地の有無、家の大きさ、仕様などによって、金額はさまざま。
税制も複雑なので、一概に「いくらならどんな家が建てられる」と言えないのが現状です。
しかし、コスト変動の要因が多い分、注文住宅にかかる費用の総額は工夫次第で抑えることができるとも言えます。
どこに予算をかけたいかという考えを明確にしたうえで、正しい知識を身につけて、納得のいく家づくりを叶えてください。